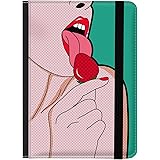坂本龍馬の生い立ち〜土佐の郷士から維新の志士へ
土佐藩郷士の家に生まれた龍馬の少年時代と、剣術修行を通じて培われた人間性
天保6年(1835年)、坂本龍馬は土佐藩の城下町高知に生まれました。坂本家は郷士という、武士の中でも比較的身分の低い階級でしたが、質屋や酒造業を営む商才に長けた一族でした。龍馬の父・八平は温厚な性格で、母・幸は龍馬が生まれてまもなく病気で亡くなってしまいます。そのため、龍馬は姉の乙女に育てられることになりました。
幼い頃の龍馬は、決して優等生とは言えない子どもでした。寺子屋では勉強についていけず、よく泣いて帰ってくることもあったといいます。しかし、持ち前の明るさと人懐っこい性格で、周囲の人々に愛されて育ちました。特に姉の乙女は龍馬を溺愛し、男勝りな性格で龍馬に武芸を教えるなど、後の龍馬の行動力の源となる影響を与えました。
14歳になった龍馬は、土佐の剣術道場「日根野弁治道場」に入門します。ここで小栗流の剣術を学んだ龍馬は、持ち前の運動神経の良さを発揮し、めきめきと腕を上げていきました。剣術修行を通じて、龍馬は多くの同輩や先輩と交流を深め、コミュニケーション能力を磨いていきます。この時期に培われた人とのつながりを大切にする姿勢が、後に薩長同盟の仲介という大役を成し遂げる基盤となったのです。
脱藩という大胆な決断から薩長同盟の仲介まで、時代を動かした龍馬の軌跡
嘉永6年(1853年)、ペリーの黒船来航によって日本中が騒然となる中、19歳の龍馬は剣術修行のため江戸に向かいました。千葉定吉の道場「玄武館」で北辰一刀流を学んだ龍馬は、ここで千葉定吉の娘・佐那と恋仲になります。しかし、江戸で見聞きした国内外の情勢は、龍馬の心に大きな変化をもたらしました。攘夷か開国かで揺れる時代の中で、龍馬は次第に日本の将来について真剣に考えるようになったのです。
土佐に帰国した龍馬は、藩の政治改革を目指す土佐勤王党に加盟します。しかし、藩内の保守派との対立が激化する中、龍馬は文久2年(1862年)に脱藩という大胆な行動に出ます。当時、脱藩は死罪にも値する重罪でしたが、龍馬は「日本を今一度せんたくいたし申候」という壮大な志を抱いていました。脱藩後の龍馬は、勝海舟に師事して海軍の必要性を学び、やがて薩摩藩の支援を受けて亀山社中(後の海援隊)を結成します。
龍馬の最も大きな功績は、慶応2年(1866年)に実現させた薩長同盟でしょう。それまで犬猿の仲だった薩摩藩と長州藩を、龍馬は巧みな交渉力で結びつけました。薩摩の西郷隆盛、長州の桂小五郎(木戸孝允)という両藩の重要人物の間に立ち、お互いの利害を調整しながら同盟を成立させたのです。この同盟こそが明治維新の原動力となり、徳川幕府の終焉へと導く決定的な転換点となりました。郷士という低い身分から出発した龍馬が、ついに日本の歴史を動かす大きな役割を果たしたのです。