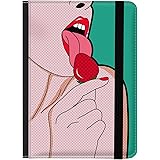龍馬暗殺の謎〜新撰組犯行説を検証する
新撰組が龍馬を狙った理由とは?幕府の意向と隊内事情から探る真相
慶応3年(1867年)11月15日、坂本龍馬が京都の近江屋で暗殺された事件は、日本史上最大の謎の一つとして語り継がれています。犯人として最も有力視されているのが新撰組ですが、果たして彼らが龍馬を狙う動機は本当にあったのでしょうか。当時の政治情勢を振り返ると、龍馬は薩長同盟の仲介役として幕府にとって極めて危険な存在でした。
新撰組は「誠」の旗印のもと、京都の治安維持を任務とする幕府直属の組織でした。局長の近藤勇や副長の土方歳三らは、尊王攘夷派の志士たちを次々と粛清し、「壬生の狼」として恐れられていました。龍馬もまた、彼らにとっては討伐すべき対象の一人だったのです。特に龍馬が推進していた大政奉還構想は、幕府の権威を根底から覆すものであり、新撰組の存在意義をも脅かすものでした。
しかし、新撰組内部の事情も複雑でした。慶応3年の時点で、新撰組は組織としての結束力が衰え始めており、隊士の脱走が相次いでいました。また、幕府からの資金援助も滞りがちで、組織の維持すら困難な状況にありました。このような状況下で、龍馬暗殺という大胆な作戦を実行する余力があったのか、疑問視する研究者も少なくありません。
目撃証言と物的証拠を徹底分析〜近江屋事件の現場に残された手がかり
近江屋事件の現場検証において、最も注目すべきは刀傷の特徴です。龍馬と中岡慎太郎の遺体に残された刀傷を分析すると、使用された刀は複数本あり、しかも相当な腕前の剣士によるものと推測されます。特に龍馬の額から鼻梁にかけての一太刀は、一撃で致命傷を与える見事な技で、これは新撰組の剣術レベルと合致するという見方があります。また、現場に残された下駄の跡や足音の証言からも、複数の襲撃者がいたことが窺えます。
事件当夜の目撃証言も興味深い手がかりを提供しています。近江屋の使用人や近隣住民の証言によると、事件の前後に怪しい人影が目撃されており、その中には新撰組の羽織を着た人物がいたという話もあります。ただし、これらの証言は事件から時間が経ってから収集されたものが多く、記憶の曖昧さや後の憶測が混入している可能性も否定できません。当時の混乱した政治情勢の中で、正確な証言を得ることの難しさが浮き彫りになります。
物的証拠として最も重要視されているのが、現場に残された鞘です。この鞘は新撰組が使用していたものと酷似しており、犯行説の根拠の一つとされています。しかし、当時の京都では同様の鞘を使用する武士は多数おり、これだけで新撰組の犯行と断定するのは早計かもしれません。さらに、新撰組ほどの組織であれば、証拠隠滅はより徹底的に行われたはずだという反論もあり、物的証拠の解釈をめぐって研究者の間で議論が続いています。