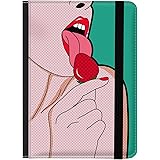龍馬最期の日〜1867年11月15日に何が起きたのか
近江屋での運命の夜〜龍馬と中岡慎太郎を襲った刺客の正体
慶応3年(1867年)11月15日の夜、京都河原町通蛸薬師下ルにあった醤油商・近江屋の2階で、坂本龍馬は土佐藩の同志である中岡慎太郎と密談を交わしていました。この日は龍馬にとって33回目の誕生日でした。午後8時頃、「十津川郷士」と名乗る数名の男たちが近江屋を訪れ、龍馬との面会を求めました。店の主人である井口新助は、龍馬が在宅していることを否定しましたが、刺客たちは強引に2階へと上がっていきました。
2階の6畳間で龍馬と中岡が話していたところ、突然襖が開かれ、刺客たちが乱入しました。龍馬は咄嗟に刀に手をかけましたが、狭い室内では十分に抜刀することができませんでした。最初の一撃で額から鼻梁にかけて深い傷を負い、続く攻撃で後頭部を袈裟懸けに斬られました。中岡慎太郎も激しい攻撃を受け、龍馬よりも重傷を負いました。事件は僅か数分で終わり、刺客たちは素早く現場から姿を消しました。
龍馬は即死状態でしたが、中岡は意識を保っており、駆けつけた人々に事件の状況を証言することができました。しかし、中岡も2日後の11月17日に息を引き取りました。この暗殺事件により、明治維新の立役者として活躍していた龍馬の波乱に満ちた33年の生涯は突然の終わりを迎えることになったのです。現場には血痕と共に、龍馬愛用の拳銃や書類が散乱しており、計画的な暗殺であったことを物語っていました。
暗殺の真相に迫る〜見廻組説と薩摩藩説、今も続く歴史の謎
龍馬暗殺の犯人については、長年にわたって様々な説が唱えられてきました。最も有力とされているのが京都見廻組犯行説です。見廻組は幕府直属の治安維持組織で、隊士の今井信郎が明治になってから龍馬暗殺への関与を自供しています。今井の証言によれば、見廻組の佐々木只三郎、今井信郎、渡辺吉太郎らが実行犯として近江屋に向かい、龍馬と中岡を襲撃したとされています。この説は物証こそ少ないものの、当時の政治情勢や見廻組の活動実態と合致する部分が多く、現在でも最も信憑性が高いとされています。
一方で、薩摩藩黒幕説も根強く支持されています。この説では、龍馬が大政奉還後の新政府構想において薩摩藩の利害と対立するようになったため、薩摩藩が龍馬を排除したとされています。龍馬は公議政体論を支持し、武力倒幕を急ぐ薩摩藩とは異なる政治路線を歩んでいました。また、龍馬が徳川慶喜の政治的復活を画策していたという情報もあり、これが薩摩藩の警戒心を招いたという見方もあります。ただし、薩摩藩説については直接的な証拠が乏しく、推測の域を出ない部分が多いのも事実です。
現在に至るまで、龍馬暗殺の真相は完全には解明されていません。史料の散逸や関係者の証言の矛盾、政治的な思惑なども絡み、歴史の謎として語り継がれています。近年では新たな史料の発見や研究手法の進歩により、従来の定説が見直される場合もありますが、決定的な証拠の発見には至っていません。龍馬という日本史上の重要人物の最期を巡る謎は、今もなお多くの研究者や歴史愛好家の関心を集め続けており、様々な角度から検証が続けられているのです。