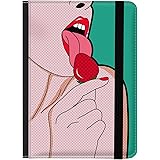龍馬の酒豪伝説〜土佐っぽらしい豪快なエピソード
一升瓶を片手に談判!薩長同盟の密談でも酒が手放せなかった龍馬
坂本龍馬といえば、幕末の志士として名を馳せた土佐の英雄ですが、実は大変な酒豪としても知られていました。特に有名なのが、薩長同盟の仲介を行った際のエピソードです。西郷隆盛と桂小五郎(木戸孝允)という犬猿の仲だった両藩の重要人物を引き合わせる重要な場面で、龍馬は一升瓶を片手に現れたと伝えられています。緊張感漂う歴史的な会談の席で、この豪快な振る舞いは周囲を驚かせました。
龍馬は酒を酌み交わしながら、両者の間を取り持ったといいます。「まあまあ、こがん堅いこと言わんと、一杯やりましょうや」と土佐弁で場を和ませ、酒の力を借りて互いの本音を引き出していったのです。この時代、酒は単なる嗜好品ではなく、人と人とを結ぶ重要なコミュニケーションツールでした。龍馬はその効果を熟知しており、政治的な駆け引きの場でも積極的に活用していたのです。
興味深いことに、龍馬自身は酒を飲みながらも決して判断力を失うことがありませんでした。むしろ酒が入ることで、相手の警戒心を解き、本音を聞き出すのが上手だったと言われています。薩長同盟という日本の歴史を大きく変えた出来事の陰に、龍馬の「酒を使った外交術」があったというのは、いかにも土佐らしい豪快なエピソードと言えるでしょう。
土佐の宴会で百杯飲み干し?仲間たちも舌を巻いた驚異の酒量エピソード
龍馬の酒豪ぶりを物語る最も有名な逸話が、土佐藩の同志たちとの宴会での「百杯飲み干し伝説」です。ある夜、土佐勤王党の仲間たちと酒席を囲んだ龍馬は、次から次へと杯を重ね、ついには百杯近くを飲み干したと伝えられています。当時の杯は現在のおちょこよりも小さかったとはいえ、その酒量は尋常ではありません。居合わせた武市半平太や中岡慎太郎といった名だたる志士たちも、龍馬の飲みっぷりには舌を巻いたといいます。
この驚異的な酒量の背景には、土佐藩特有の酒文化がありました。土佐は「酒国土佐」と呼ばれるほど酒造りが盛んで、武士たちの間でも酒量の多さが一種のステータスシンボルとされていました。龍馬はその土佐気質を体現する存在として、仲間たちから一目置かれる存在だったのです。また、当時の土佐の酒は度数がそれほど高くなく、現在の日本酒とは製法も異なっていたため、大量に飲むことも可能だったと考えられています。
しかし、龍馬の真骨頂は単に大量に飲むことではありませんでした。どれだけ飲んでも翌朝にはけろりとして、いつもと変わらぬ調子で政治活動に励んでいたのです。「昨夜はえらい飲んだのう」と笑いながら、重要な書状をしたためたり、商談に出かけたりする姿は、まさに土佐っ子らしい豪快さの象徴でした。この底抜けに明るい性格と驚異的な酒量が、龍馬を慕う人々を増やし、後の大政奉還への道筋を作る人脈形成にも大いに役立ったのかもしれません。